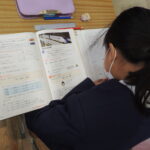5月1日(水)、「理科室から出火」という想定で、今年度、最初の避難訓練を行いました。事前に各学級で、避難経路と避難時の注意について、確認しました。避難時の注意は、「お…押さない」、「は…走らない」、「し…しゃべらない」、「も…戻らない」です。これらは、二次災害を防ぐ点でも重要です。子どもたちは、避難訓練の目的とそのための行動について理解し、真剣に取り組みました。学校以外の様々な場所でも災害にあったときに、子どもたちが自ら考え、判断し、行動できる力を身につけるために、ご家庭でもお話をする機会をもっていただければ幸いです。
トピックス
交通安全教室
4月19日(金)、たつの警察署と越部駐在所、交通安全協会の方々のご指導で、交通安全教室を行いました。まず、登校班での歩行訓練では、登校旗の使い方や安全確認の仕方などの説明を聞き、指導を受けながら、信号機を設置した運動場の横断歩道を歩きました。その後、今年は実際に車道にある横断歩道に行き、学んだことを生かして渡りました。最後に、自転車の乗り方を警察の方の模範演技を見て学びました。そして、自転車の点検項目として、「ぶ・た・は・しゃ・べる」も学びました。警察庁の情報では、歩行中の小学生の事故は、1年生が最も多く、また発生月ごとでは、5月が最も多いようです。その理由は、「1年生は小学校に入学し、5月には行動範囲が広がり、『一人歩きデビュー』の時期である」などです。かけがえのない大切な命、事故にあわないようにご家庭でもお話をしていただきたいと思います。
1年生を迎える会
4月17日(水)、6年生が中心になって、「1年生を迎える会」を開催しました。拍手の中、1年生は嬉しそうにアーチをくぐって入場しました。歓迎の言葉の後、6年生が「入学おめでとう」の気持ちを込めたペンダントを1年生一人ずつ首にかけていきました。そして、越部小学校を紹介するクイズや、「越部っ子憲章」の内容の寸劇で、楽しく、わかりやすく伝えました。笑顔いっぱいの時間を過ごした1年生は、終わりの言葉の後、退場しました。6年生は始業式以降の短期間でしたが、アイデアを出し合い、協力して準備したり、責任をもって役割を進めたりして、最高学年としての素晴らしい活躍でした。全校児童の温かい気持ちが伝わる会になりました。
今年度、最初の給食
4月15日(月)、今年度、最初の給食の日、1年生にとっては、小学校での初めての給食でした。6年生が準備のお手伝いに来て、手際よく配膳しました。さすが6年生でした。準備が整い、6年生の「いただきます」の声に続いて、挨拶をしました。お祝いのデザートもあり、おいしくいただきました。その後は、6年生の当番が交替したり、6年生の手助けを受けながら、1年生はそれぞれの仕事を教えてもらったりし、今では自分たちで準備や後片づけができるようになりました。6年生の優しさが1年生に伝わり、5年後には今度は教える立場になり、1年生へとつながっていきます。
令和6年度のはじまりにあたって
春爛漫の4月、令和6年度が始まりました。保護者の皆様、地域の皆様には、本校の教育活動の進展並びに充実のために、ご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。
4月8日(月)、校庭の桜が満開の中、子どもたちは登校班長を先頭に上手に並び、新しい学年に期待を膨らませて登校しました。子どもたちは、久しぶりに友だちと会えて、教室で嬉しそうに話をしたり、早速、運動場で楽しく遊んだりしていました。
着任式で転入された先生方を温かく迎え、始業式では、校訓「みがこう あかるく たくましく」と「越部っ子憲章」をもとに、「いのちを大切にする-自分、まわりの人、もの」、「優しい心をもって、笑顔で明るく-返事・あいさつ」、「目標をもって、自ら学び続ける。みんなで協力して、よりよい学級・学年、学校をつくる。」の話をしました。その後、4~6年生は入学式の会場準備や周辺の掃除を張り切って進めていました。2・3年生は、教室でそれぞれのスタートを頑張っていました。
小雨交じりの4月9日(火)の入学式。新1年生19名がわくわくどきどきしながら、入学式に臨み、「はい」の返事や「ありがとう」の言葉をしっかりと伝え、最後までよく頑張りました。6年生は、1年生と手をつないで入場したり、花のアーチをつくったり、歓迎の言葉を伝えたりして、最高学年として、素晴らしい態度で活躍しました。ご来賓の皆様、保護者の皆様、ご臨席賜り、ありがとうございました。
全校児童141名。校訓と「越部っ子憲章」を基盤に据え、教職員全員が協力して、子どもたちが夢や志を抱き、ふるさと「越部」を愛し、「豊かな心」「健やかな体」「確かな学力」の調和のとれた「生きる力」を培っていきます。そして、自分の力を発揮し、仲間とともに力を合わせ、「在りたい未来」を創造する力を育んでいきます。
保護者の皆様や地域の皆様との連携を深め、小中一貫校を見据えて、校歌に歌われている校庭のせんだんの木のように、地域に根をはり、地域に開かれた学校、地域とともに歩む学校をめざしていきます。本年度も、保護者の皆様、地域の皆様の本校教育活動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
新たなステージでの活躍を願って
春の柔らかな日差しに、色とりどりの花が美しく輝き、校庭の桜の花も咲き始めました。
卒業と修了、学校生活における「節目」を迎えました。3月21日(木)、卒業証書授与式を挙行し、優しさと行動力をもって歩んできた6年生は、148年の長きに亘って刻み続けてきた越部小学校卒業生の歴史に名前を記す卒業証書を授与されました。6年間の総まとめとして、一人一人の「みんなでよい卒業式にしよう」という思いが一つに結実した素晴らしい姿でした。そして、保護者の皆様や地域の皆様にその成長した姿をご覧いただくことができました。卒業生は「越部小学校最高学年」のたすきを5年生に渡し、小学校との別れを惜しみつつ、数多くの思い出とこれからの夢や希望を胸に巣立っていきました。
22日(金)、目標を持って、それぞれの頑張りが光った1年生から5年生は、修了式を行い、1年間の課程を修了しました。その姿には、「頑張ってきた」という自信や達成感が表れていました。
新型コロナウイルスが感染症法上の第五類に移行された5月以降、インフルエンザによる欠席や学年閉鎖がありましたが、子どもたちが元気に登校し、学習活動を進めるにあたり、保護者の皆様には日々の健康管理や健康観察、必要に応じた感染対策やお願いなど、様々な場面でご支援とご協力をいただき、ありがとうございました。おかげさまで子どもたちは成長することができました。
PTA活動では、会長様をはじめ、本部役員様、各部長様、各部員の皆様にご尽力いただき、全てのPTA会員の皆様にお世話になりましたことに心よりお礼申し上げます。地域の皆様には、子どもたちの安全・安心なくらしのために、見守りいただきましたこと、深く感謝申し上げます。
4月、卒業した23名は皆様にお支えいただいたことを胸に抱き、夢や志を持って歩んでいくことと信じています。1年生から5年生はそれぞれ進級し、新しい学年で新1年生を迎え、新たな気持ちで目標をもって新年度のスタートがきれることを願っています。
6年生を送る会
3月1日(金)、5年生が中心となって開催した「6年生を送る会」では、それぞれの学年が、工夫を凝らした歌やクイズ、劇、ゲームなどで6年生と楽しい時間を過ごしました。そして、登下校や委員会などでお世話になったことを感謝の言葉として、伝えました。5年生は会を運営する準備をし、様々な役割をしっかりと務め、「4月からは私たちが引き継いでいきます。」という力強い言葉がありました。1年前は送る側だったのが、送られる側になった6年生。最上級生としての役割をしっかりと果たすことができたからこそ、5年生のこの言葉になったのだと思います。思いや願いをつなぐ「たすき(越部小の伝統)」を次に渡すこと、受け取ることの大切さや重みを相互に感じ合えました。最後に、6年生からはお礼と中学校での決意、みんなへのエールがありました。「ありがとう」の感謝の言葉が幾重にも重なり、優しく、温かい気持ちが通い合った「6年生を送る会」になりました。
3年生 せんだん発表会
3年生が「せんだん」の学習で学んだ昆虫(カブトムシ)に関することと越部探検隊での地域学習をタブレットにまとめ、お世話になった講師の方と来年度学習する2年生に発表しました。自分たちが体験したり、現地に行き、聞いたりしたことをクイズ形式など伝え方を工夫して、楽しく理解してもらえるようにしていました。2年生は、興味深く聞き、喜んでクイズに答えていました。「越部っ子憲章」第6条のふるさとを知り、ふるさとを大切に思う気持ちが育まれ、次の学年へとつながっています。
1年生6年生との交流会
1年生がお世話になった6年生をおもちゃパークに招待しました。6年生は、どんぐりやまつぼっくりなど秋のものを使ったつりゲームやボウリングなど1年生が工夫して作ったおもちゃを使って、一緒に遊び、笑顔がはじけていました。楽しい思い出がまた1つ増えました。
2月 学年のまとめと次学年に向けて
「1月(行く)、2月(逃げる)、3月(去る)」という言葉がありますように、早いもので、2月も半ばです。「立春」を過ぎ、梅のたよりが届くようになり、日中、暖かい日もあります。
3学期始業式で子どもたちに、今学期間の3つの大切なこととして、「学年のまとめ・次の学年への準備・次につなぐ(引き継ぐ)」の話をしました。
子どもたちは、学年のまとめと次の学年に向けて、学習を進めたり、復習をしたり、生活を見つめ直したりしています。また、休み時間には、運動場で縄跳びやサッカー、ドッジビーなどで楽しく遊んでいます。
「教育」を「共育」や「響育」とあてた言葉があります。「共育・・・子どもと共に大人も育つ」、「響育・・・心と心が響き合って育つ」という意味です。この時期に、改めて振り返ってみる視点であり、そして、来年度に向けて大切にしたいことでもあります。
今月も健康管理をはじめ、教育活動へのご支援ご協力をよろしくお願いいたします。