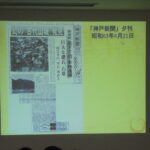ひまわりの花が咲き、いよいよ梅雨明けが近づいてきました。4月、始業式・入学式をそれぞれ学年のスタートとして、子どもたちとともに、新しい気持ちで進めてきた1学期が終わりました。
保護者の皆様には、1学期間、教育活動の推進と充実にご支援ご協力を賜り、誠にありがとうございました。また、先日は、個別懇談会にご出席いただき、重ねてお礼申し上げます。地域の皆様には、子どもたちの安全・安心な生活のために、見守りなど大変お世話になり、心より感謝申し上げます。
学習や生活、運動、行事などにおいて、子どもたち一人一人が、或いは、仲間とともに、活躍する姿や頑張る姿、まわりの人に優しく接している姿が数多くありました。授業参観や運動会などでもその姿をご覧いただいたことと思います。めあてをもって、取り組んでいる子どもたちは、真剣なまなざしや溢れんばかりの笑顔が光っていました。また、失敗や間違いがあっても、あきらめずに努力を重ねている姿や、新たなことにチャレンジしようとする姿など、たくましく歩みを進めました。校外においても、力を発揮しました。
その基盤にあるのが、「越部っ子憲章」です。制定から10年、「越部っ子憲章」は、未来を担う子どもたちを健やかに育む学校・家庭・地域の共通の指針です。
夏休みは、学びの場が、家庭や地域になります。
「越部っ子憲章」を基に、大切な命を守り、「自律」と「自立」に向けて、得意な学習を伸ばす、苦手な学習を克服する、家族の一員としての家の仕事(手伝い)を継続する、規則正しい生活を続けるなど、子どもたちが生活のリズムを保ち、めあてをもって取り組んだり、安全に生活したりできますように、ご家庭でもお話をする機会をお願いします。
水の事故や交通事故、熱中症などに留意され、ご家族皆様が健康に過ごされ、課題提出日や2学期始業式に元気な顔で会えますことを心より願っております。