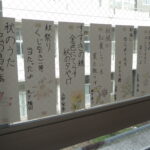10月25日(水)、4年生が「せんだん(総合的な学習)」の学習で皮革工場の見学に行きました。原皮が洗浄やなめし、染色などの職人の方々の技術による多くの工程を経て、「皮から革へ」となっていく様子を興味深く見ました。また、実際に革に触って感触や風合いを感じるなど、五感を通しても学び、革製品の良さや職人の方々の工夫や苦労などの話を聞いたり、質問したりして、その思いに触れ、共感しました。
投稿者: 越部小学校
3~6年生 スマホ・ケータイ教室
10月23日(月)、3~6年生が兵庫県警学生サイバー防犯リーダーの大学生と兵庫県警少年サポートセンターの方々から、インターネットやSNS、ゲームなどの注意すべきことを学びました。動画を視聴した後、近くの友だちと話し合い、意見を発表しました。SNSでの誹謗・中傷やデマの拡散では、法的な罰則も踏まえた話に表情が真剣になり、ゲーム依存の問題点については、自制心の必要性を感じていました。児童それぞれが「自分はどうするか」という視点で考えることができました。
音楽会・市民童謡ふれあいコンサート
10月20日(金)、音楽会のスローガン「はずめ歌声 ひびけ合奏 さかせよう 笑顔の越部音楽会」のもと、今年は、低・中・高の学年部ごとに演奏と合唱の練習を重ねてきました。音楽会で合唱をするのは4年ぶりでした。コロナ禍の中、児童は多くの人の前で歌うことがほとんどなかったので、歌唱の仕方を学び、少しずつ慣れていきました。そして、「こども音楽会」では、お互いに聴き合うことで、演奏や合唱に対しての気持ちの入り方が一段上がりました。「練習の成果を発揮しよう」、「思いや願いを歌詞やメロディーに込めて届けよう」当日、児童の一生懸命な姿と歌声、奏でる曲が心に響いてきました。また、UTAHIMEの皆様には趣向を凝らした演出とともに素敵な歌声を聴かせていただきました。
そして、6年に1回の「市民童謡ふれあいコンサート」では、プロ歌手の方に、昔からの童謡をはじめ、たつの市で新しくできた童謡など披露していただきました。児童は歌を一緒に歌ったり、体でリズムをとったり、手拍子をしたりして、それぞれがとても楽しんでいました。特別に歌っていただいた「越部っ子憲章の歌」では、児童はとても嬉しそうに歌い、体育館中に響く大合唱に「越部っ子」の気持ちが込められていました。
児童と保護者の皆様、ご来賓の皆様、地域の皆様とともに「芸術・文化の秋」を共有できたことを大変嬉しく思います。ご支援ご協力に深く感謝申し上げます。
6年生 地域拠点型合同防災訓練
10月4日(水)今年も6年生が、龍野北高校で開催された「地域拠点型合同防災訓練」に参加しました。高校生に加わり、災害が起きた時、道具を使って、がれきを取り除く方法や人を運ぶ方法などを教えていただき、体験もしました。地域が連携した防災・減災の必要性とともに、日ごろから備えておくことの大切さを感じた半日になりました。
深まりゆく秋 体験や交流が 心の成長に
11月になりました。木々の葉が日ごとに色づき、秋が深まってきました。秋晴れの空と澄み切った空気が気持ちよく感じられたり、夜空に見える月や星が美しく感じられたりします。2学期の折り返しを過ぎ、今月は、オープンスクール・参観・PTA教育講演会、マラソン大会などを予定しています。先月から、学年に応じて、講師を招いての様々な体験や地域との交流を通した学習を行っています。日々の学習の力が体験学習や交流活動の場面で生かされたり、体験や交流で培った力が教室での学習にフィードバックできるように進めたりしています。五感を通して共感的に学ぶことが心の成長につながることを願っています。この時期、寒暖の差が大きく、市内ではインフルエンザが増えている状況ですので、引き続き、健康管理・観察にご協力をよろしくお願いいたします。
6年生 STEAM教育推進事業
9月22日(金)、6年生が兵庫県立大学大学院特任教授園部先生から、「アメーバの観察」について教えていただきました。細胞の説明や単細胞生物であるアメーバの増え方などのお話を聞いたり、スライドガラスに乗せたアメーバを電気顕微鏡で観察したりする子どもたちは、興味津々でした。アメーバに与えたえさが体内で動いている様子も観察し、驚きの声があがっていました。将来に向けてのキャリア教育の視点からも意義深い授業でした。
実りの秋 持てる力をさまざまな場面で発揮して!
朝夕の空気や虫の音、稲穂の実りをはじめ、百人一首の和歌「秋風に たなびく雲の たえ間より もれいずる月の 影のさやけさ」にもあるように、秋の情景の美しさが感じられるようになりました。9月29日、今年の「中秋の名月」は美しい満月でした。秋は、「読書の秋」、「スポーツの秋」、「芸術の秋」・・・とあるように、何をするにもよい季節です。子どもたちには今まで以上に一日一日を大切に過ごしてほしいと思います。
さて、5年生が自然学校(自然体験活動)を行い、自然の中での様々な活動を通して、多くの学びや気づきがあり、成長につながる機会になりました。また、6年生の修学旅行では、歴史と文化を大切にする心情や友情、公共マナーなどを培うとともに、心に残る思い出を作ることができました。いずれも子どもたちが元気に参加し、充実した活動にすることができました。どうもありがとうございました。
20日(金)は、音楽会と、6年に1回のプロの歌手による市民童謡ふれあいコンサートを開催します。「みんなで創り上げる」、「心を込めた歌と演奏を届けよう」など、子どもたちのよさが光るようにしていきたいと考えています。そして、日々の学習をはじめ、様々な体験や交流の機会を通して、子どもたちが自分自身を見つめ直したり、周囲の人とつながることの大切さを実感したり、可能性の幅を広げたりして、「実りの秋」として、一段と成長する機会にしてほしいと願っています。今月もご支援とご協力をよろしくお願いいたします。
*「秋風に たなびく雲の たえ間より もれいずる月の 影のさやけさ」(「秋風が吹いて、たなびいている雲の切れ間からもれ出てくる月の光は、なんという澄み切った明るさでしょう」・左京大夫顕輔)
1・2年生 動物愛護教室
9月27日(水)、動物愛護センターの方々からかけがえのない命についてのお話を聞きました。自分や友だち、犬の心臓が脈打つ音を聞き、命の鼓動を感じたり、犬とのふれあいを通して、温かさや優しさの大切さに気づいたりしました。また、動物を飼うときの心得についても教えていただきました。
3・4年生 体力アップサポーター教室
9月22日(金)、講師の先生の指導により、3・4年生が器械体操(マット運動)を教えていただきました。マット上で体をゆりかごのように揺らしたり、マットに傾斜をつけて回転したりして、スモールステップで後転や開脚前転などの技が上手にできるようになっていきました。全3回、次回は1・2年生です。
6年生 修学旅行
6年生は、9月14日(木)・15日(金)の1泊2日、日本の2つの都であった奈良と京都に修学旅行に行きました。法隆寺や大仏様、銀閣、金閣、二条城などを興味深く見たり、熱心に話を聞いて記録したりして、正に歴史を感じ、歴史にふれた時間を過ごしました。事前に歴史講座で、講師の方から、見どころや越部地区とのつながりなどのお話を聞いていたので、理解が深まりました。そして、「温故知新」の言葉のように、歴史の舞台に立ち、本物と出会い、先人の思いや願いを想像したり、今につながる技術や文化の一端を学んだりしたことは、これからの学習はもとより、今の生活を振り返り、未来に向けての考え方や工夫などにつながっていくと思います。そして、きまりやマナーを守り、それぞれが自分の役割を果たし、バスの中での活動やグループでの活動、旅館でのひとときなど、友だちと笑顔一杯に過ごした楽しい時間もかけがえのない思い出になりました。保護者の皆様には、健康管理や準備など、ご支援ご協力をいただきましたことに深く感謝申し上げます。